この記事では、行動心理学を利用した「消費者心理をつかむテクニック」について解説しています。
人の心を動かす文章を書く際に大切なのは、人間の「脳の働き」や「思考のクセ」を知ることです。
なぜなら、人は「動物的直感」で欲しいと思い、「人間的理性」を正当化することで購入を決断するからです。
この記事では、セールスコピーを書く際に効果的に心理テクニックについて書きます。
今回の記事でお伝えする「行動心理学」の要素を使えば、「マーケィング」だけでなく手紙やメールや対面で「人間関係」を良好にするのにも役立つので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
行動心理学とは?どんな意味がある?
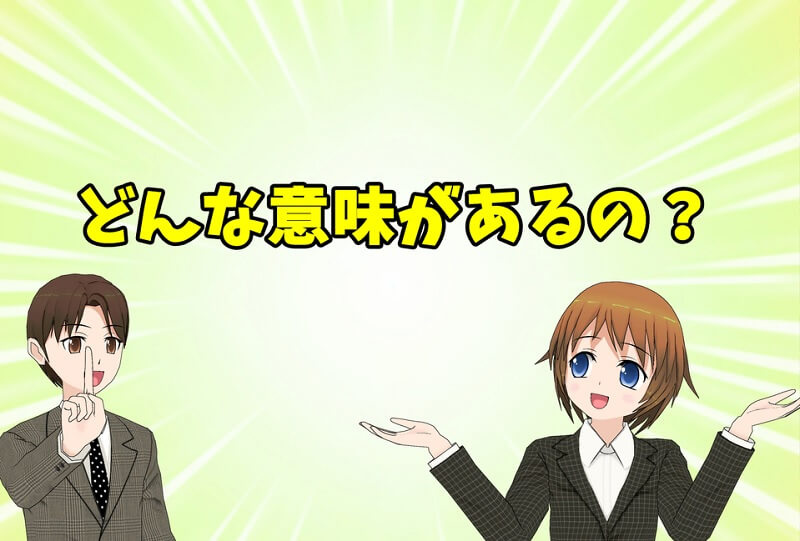
行動心理学とは「人間のある行動を観察し、その時にどういった心理にあったのかを分析する学問」です。
人間の持つ基本的な「欲求」や「心理」は、人種、国籍、時代を超えて普遍的なものです。
その欲求や心理を、経済活動やマーケティングの視点から分析し体型化したものが「行動心理学(行動経済学)」です。
たとえば、下記のようなことを分析します。
- ほしいと思った商品を「どのようなきっかけ」で購入したのか?
- 毎月定期購入していた商品を「なぜ解約した」のか?
- どうしても欲しかったはずの商品を「なぜ後回しにした」のか?
つまり、人が何を考えその行動を取る決心をしたのか?その行動に伴う「心理状態」や「仕組み」を分析するわけです。
行動心理学はダイレクトレスポンスマーケティング(DRM)と相性抜群
行動心理学は「直接個々の消費者にアプローチをして反応を得る」ことになる、ダイレクトレスポンスマーケティングにおいて重要な考え方となります。
なぜなら、人が行動に至る「意思決定の過程」を知っておくことが、人を動かすためには必須となるからです。
冒頭にも書きましたが人は「動物的直感」で欲しいと思い、「人間的理性」を正当化することで購入を決断します。
『心脳マーケティング』(ジェラルド・ザルトマン著)によると、人間の思考や行動のうち意識下での自覚はわずか5%に過ぎず、残りの95%は無意識下だと言われています。
わかりやすく言うと、人が商品やサービスを買う瞬間というのは、無意識化で95%が決定されるということですね。
この法則はセールスコピーを書く際に知っておく必要がある重要なポイントです。
人間心理を理解しないまま上辺のテクニックに酔った文章を書いても、自己満足なだけの文章になるので注意が必要です。
この後、行動心理学のテクニックを詳しくお伝えしていくので、「読者の悩みを解決するために消費者心理をつかむテクニックを知る」という意識で読んでみてください。
今日から使える心理トリガーを使ったテクニック16選
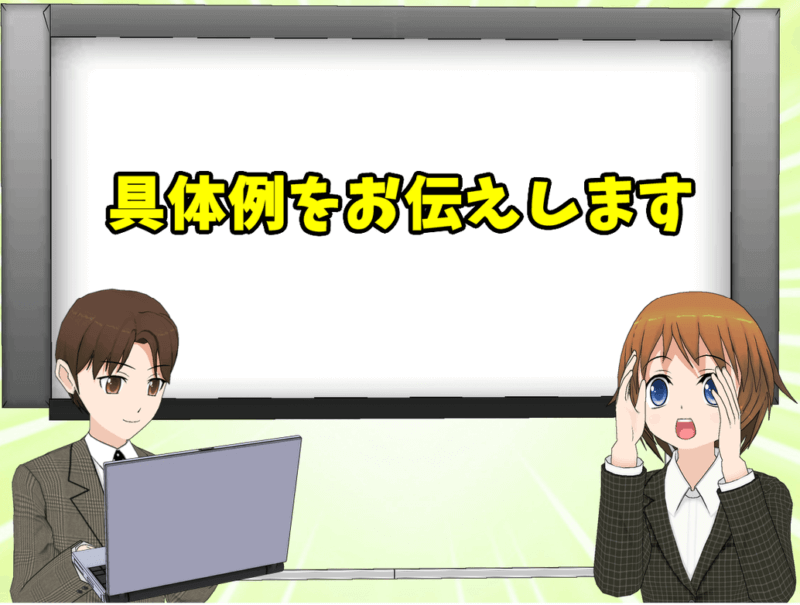
ダイレクトレスポンスマーケティングでは「具体的に人の感情を動かす方法」のことを心理トリガーと呼びます。
心理トリガーとは、顧客が何かを購入するときの「きっかけ」「決め手」になるような心理的な仕掛けのことです。
心理トリガーとなるテクニックはたくさんありますが、今回はその中でも「使いやすいもの」を厳選してお伝えしていきます。
具体的には、下記の16個のテクニックをお伝えしていきます。
- ゴルディロックス(松竹梅)効果
- AIDMAの法則
- 理想の未来をイメージさせる(ベネフィットを伝える)
- 両面提示の法則(メリットとデメリットを伝える)
- 希少性(スノッブ効果)の法則
- バンドワゴン効果(集団心理の利用)
- 返報性の法則
- ハロー効果
- ティーザー効果
- カリギュラ効果
- ドア・インザ・フェイス
- バーナム効果
- シャルパンティエ効果
- 損失回避(プロスペクト理論)
- カクテルパーティ効果
- 認知的不協和
これらのテクニックを知った上で、文章を書いていくことで「読者の心に刺さる文章」を書けるようになります。
では、具体的に1個ずつお話ししていきますね。
心理テクニック1.ゴルディロックス効果(松竹梅理論)
1つ目のテクニックは、ゴルディロックス効果(松竹梅理論)です。
ゴルディロックス理論は、「比較サイト」などでよく使われているテクニックですね。
簡単にいうと、複数の商品を提示し、その中からこちらの意図する商品に「誘導」するテクニックのことです。
一例をあげると、飲食店などで3種類のコースを用意しているお店に行かれたことがあると思います。
多くの場合、3種類のコースを用意している理由は、日本人が基本的に真ん中の「竹コース」を選ぶ傾向がある「特性」を利用しています。
たとえば、あなたが20代前半の男性だとします。
気になっている女の子との初デートでオシャレなフレンチのお店にいったシーンをイメージしてみてください。
- 5,000円
- 7,000円
- 9,000円
上記3つのコースがあった場合、どのコースを選ぶでしょうか。
おそらく、7000円のコースを選んでしまうのではないでしょうか?
これは、お店側が男性の心理(プライド)を意識してメニューを作っているからです。
 わいず
わいず5,000円のコースを頼んだらケチだと思われるかなー。
かといって、9,000円のコースは金銭的にキツイしな…。
よし、真ん中の7,000円のコースを選んでおけば幻滅はされないだろう
上記のように、「自分のプライド」を保ちつつ「女性に嫌われない選択」をするために、ほとんどの人は真ん中の「竹」コースを選ぶ傾向にあるわけですね。
しっかりと意図を持って3コース用意しているお店の場合、「竹」コースを選んでもらったほうが、お店側が儲かるように設定しているケースが多いです。
つまり、知らず知らずのうちに誘導されているということです。
これをビジネスに置き換えると、一番売りたい商品の前後に違う価格のものを用意して提示することで、意図的に自分が本当に売りたい商品を選んでもらえる可能性が高まるわけです。
テクニック2.AIDMAの法則
2つ目のテクニックはAIDMAの法則というものです。
AIDMAの法則とは、顧客が商品を買うまでの購買心理プロセスを表した法則です。
この法則では、消費者は商品の存在を知ってから購入に至るまでに5段階の心理変化があると言われています。
- Attention(注意)
- Interest(関心)
- Desire(欲求)
- Memory(記憶)
- Action(行動)
ここでのポイントは、人間は何かを購入する際に「理屈」だけで購入するわけではないということです。
人間は、「感情」で欲しいと感じ「理論」で自分の購買意欲を正当化することで購入にいたります。
特に、今のモノがあふれている世の中では「必要だから」という理由で購入する人は多くありません。
例えば、iPhone信者の人はiPhoneが必要だから買うのではなく「最新のiPhoneを持っている優越感」を感じたいために、新機種が発売するたびに買うわけです。
欲しい(Desire)という感情が生まれた人間は「購入する」という行動に出ます。
人間には理性がありますから「欲しい」という欲求を正当化するための理由、つまり大義名分を用意してあげる必要があるというわけです。
具体的には、「期間限定」「数量限定」という風に「今すぐに買わなければ、もう手に入らないかもしれない」という風に、後ほどお話しする「希少性の法則」と合わせて使うことで欲求を正当化してあげることもできます。
テクニック3.理想の未来をイメージさせる(ベネフィットを打ち出す)
3つ目のテクニックは、商品を使った先の未来を見せてあげるというテクニックです。
商品を販売することを考えたとき、「使ったらどうなれるのか?」という「明るい未来を見せる」ことが何よりも重要です。
ようするに、ベネフィットを伝えてあげることですね。
- メリットとベネフィットの違い
-
- メリット:商品のウリ、特徴
- ベネフィット:メリットによってもたらされる良い変化
商品販売でよくやってしまいがちな失敗は、商品のメリットをひたすら説明してしまうことです。
これではなかなか商品は売れません。
例えば、海外赴任がきっかけで英語教材を買おうとしている人は、「自由に英語を喋って、海外で活躍している自分」をイメージしています。
ところが、サイトの情報に「教材の優れている点」が延々と書いてあるだけだったらどうでしょう?
教材のメリットについて、いくら詳しく説明されていても「自分が使ったらどうなれるの?」というベネフィットが書かれていなければ、消費者は商品を欲しいと思いません。
サイト訪問者に理想の未来を与えてあげるならば
- 教材を使って人が喋れるようになったのか?
- どれくらいの期間で喋れるようになるのか?
- 愛用者の声はどんなものがあるのか?
- 英語が喋れることでどんな楽しい人生が待っているのか?
このように、商品を購入したことによるベネフィット「理想の未来像」をイメージさせてあげることが大切です。
ベネフィットとメリットの違いに関しは、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
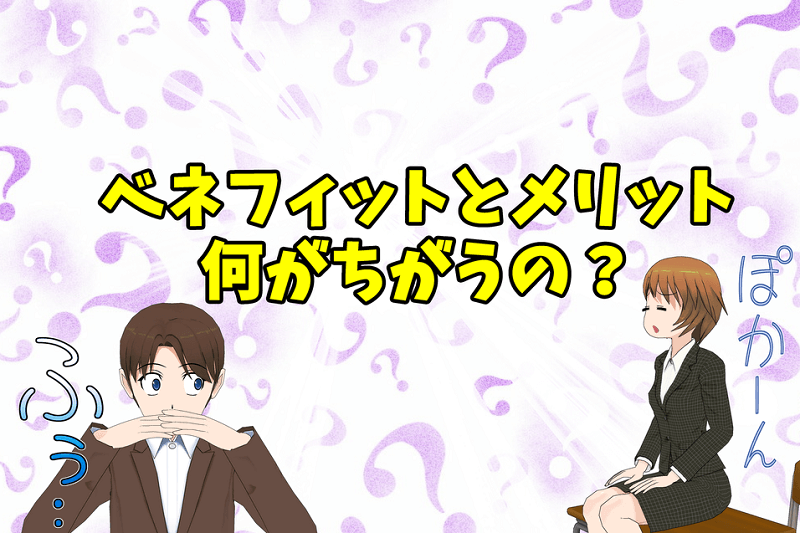
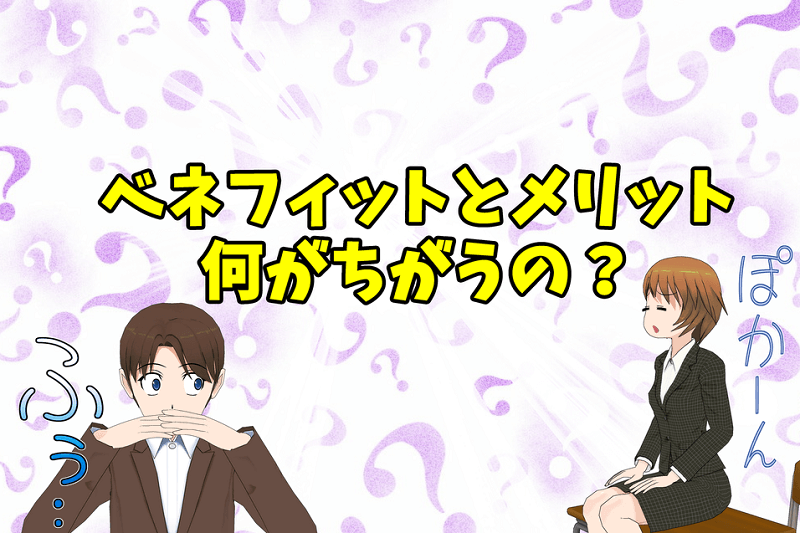
※注意※ 薬機法に気をつけましょう
あなたの扱っている商品が化粧品や健康食品などの場合、効果効能を伝えることは「薬機法」に触れてしまう可能性もありますので、商品ごとにしっかり確認してから書いてください。
テクニック4.両面提示の法則(メリットとデメリットを伝える)
4つ目のテクニックは、いい面だけではなく、悪い面も正直に伝えるということです。
両面提示という言葉は、あまり聞きなれないかもしれません。
両面提示とは、簡単にいうと下記の通りです。
- 片面提示:メリット(もしくはでメリット)しか伝えない
- 両面提示:メリットとでメリットの両方を伝える
このように、商品(サービス)のいい点だけではなく、悪い点もキチンと伝えてあげることで、読者は購入するかの判断をすることができるわけです。
たとえば、あなたが中古車ディーラーで働いていて、接客中のお客さんに車のセールスをするとします。
その時の会話はこんな感じになります。
こちらの車種は、外観もキレイで走行距離も少ない割に、お値段も安いのでおすすめです。
今なら、こちらの最新タイプのカーナビも工賃込5万円でお付けしますよ!
こちらの車種は、外観もキレイで走行距離も少ない割に、お値段も安いのでおすすめです。
今なら、こちらの最新タイプのカーナビも工賃込5万円でお付けしますよ!
心の声(実は事故車だけどね)
この場合、本当は事故車だということは、「伝えるべきでしょうか?」「黙っておくべきでしょうか?」
普通に考えたら伝えるべきですよね?
事故車であることを黙って売って、後からバレた場合、「お店の信頼は失墜」します。
反対に、「車体に影響は全くないですが、実は事故車なんです、そのかわり相場よりも「30万円」お安く設定しています。
安心してお使いいただくために3年間の無料点検もお付けしますので、事故車ではないお車と遜色な状態で乗れることはお約束します」
このようにデメリットを伝えた上で、納得して購入されるならお客さんの満足度も下がりません。
事前にきっちりデメリットを伝えることで、クレームを減らす効果もあるわけですね。
あえて欠点を提示することで、信用を得る心理効果。
これが「両面提示の法則」です。
目先の利益ではなく、長期的な視点で「信用」を得ることが利益を最大化するコツです。
テクニック5.希少性の法則
5つ目のテクニックは、珍しさを表現するというものです。
先ほども少し、お伝えしましたが、人間は「初回限定」「数量限定」というものに惹かれる傾向にあり、この心理効果の事を「希少性の法則」といいます。
この法則は、あなたもご存じのとおり、様々なところで使われている手法です。
限定とひと言でいっても、
- 数量限定
- 人数限定
- 会員限定
- 期間限定
- 地域限定
- 女性限定
- 時間限定
など、様々あります。
人はどこでも手に入るものは価値が低く、数が少ないものは価値が高いと考える傾向にあります。
その商品やサービスの本質的な価値よりも、希少性があるかどうかという漠然とした判断で選んでしまう訳ですね。
- 「数が少ないから貴重なものだ」
- 「貴重なものだから高いのは当たり前だ」
- 「高いからこそ、いいものに間違いない」
という風に、勝手に商品の価値と希少性を結び付けてしまい、価値判断をしてしまうんです。
- 希少性を打ち出していない、良質なあなたの商品
- 希少性を打ち出している、粗悪な競合の商品
であれば、希少性を打ち出している、粗悪な商品をお客さんが手に取ってしまう可能性もあるわけです。
「いいものを作ればお客さんは分かってくれる」という時代はとっくに終わりました。
良い商品は、いい商品に見えるようにも表現してあげることがお客さんのためにも重要なんですね。
テクニック6.バンドワゴン効果(集団心理の利用)


6つ目のテクニックは、バンドワゴン効果(集団心理の利用)です。
「バンドワゴン」とは行列の先頭の楽隊車のことであり「バンドワゴンに乗る」とは、時流に乗る・多勢に与する・勝ち馬に乗る、といった意味です。
人間は周りの人間がどういう判断をしているか気になるという心理があり、無意識のうちに周りの人と同じ行動をしようとします。
これをバンドワゴン効果といいます。
居酒屋にいくと、なぜか「とりあえず生」から始まりますよね?
疑問に思ったことありませんか?
本当は最初から焼酎が飲みたいのに「いきなり、焼酎を頼んだら空気がよめないやつになる」と感じてしまうため、無意識のうちに生を頼んでしまうわけです。
意志決定というものは、必ずしも自分の中で完結するわけではなく、周囲の意見に影響されてしまうのものです。
特に日本人はこの「人に影響される」といい特徴が強い傾向があります。
たとえば、
- 顧客満足度NO.1!
- 愛用者〇〇人突破!
- お客様の声掲載数、地域NO.1!
という感じで、多くの人に選ばれている人気商品であることをアピールすることで、売上アップに繋がっていくわけです。
バンドワゴン効果について、もっと詳しく知りたい場合は下記の記事で詳しく書いているので、参考にしてみてください。


やはり、多くの人に選ばれているというのは「安心感」を与えます。
ぜひ、あなたの商品が多くの方に愛用されている場合に使ってみてください。
テクニック7.返報性の法則
7つ目のテクニックは、恩返しの心理を利用するというものです。
返報性の法則とは、人は他人から何かをしてもらうと、お返しをしなくてはならないという感情を抱く心理です。
ビジネスをしている人の中には、「ギブ&テイク」ではなく、「ギブ&ギブ」が大切です。
この「先に与える」という言葉こそ、「返報性の法則」の力を表しているんですね。
たとえば、夜の世界の女性で一流になる人と二流で終わる人の違いも、この返報性の法則が関係してきます。
この話は、以前ある人から聞いた話なんですが、夜の世界で一流になる女性と二流で終わる女性の違いも返報性の法則で説明できました。
どういうことかというと、
- 一流の女性は、今が平凡でも「将来成功するかもしれない」と考え、分け隔てなく接客する
- 二流で終わる女性は、今現在一流の男を大切にする
という違いがあったんですね。
違いがわかるでしょうか?
- 二流で終わる女性は、成功者(お金になる)男性ばかりを大切にするから下心が伝わる。
- 一流になる女性の接し方は、成功者でもない自分をこんなに大切にしてくれているという「心意気」が伝わる
その結果、二流の女性からは男性が離れていき、一流の女性には、成功した男性が「あの時、世話になったから」という気持ちが働き、強力な応援団になってくれるそうです。
これが、返報性の法則です。
今お話しした例は極端な例ですが、人は何かをしてもらうと自然に、お返しをしなくてはならないと思うということですね。
返報性の法則については、下記の記事でも解説しています。
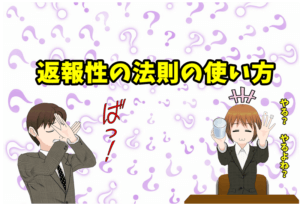
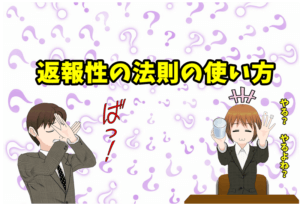
テクニック8.ハロー効果
8つ目のテクニックは、ハロー効果というテクニックです。
ハロー効果(ハローこうか、英:halo effect)とは社会心理学の現象で、ある対象を評価をする時に、それが持つ顕著な特徴に引きずられて、他の特徴についての評価が歪められる(バイアス)現象のことです。
簡単にいうと、商品を評価する時に「一番印象的な特徴が他の特徴にもいい影響を与える心理効果」です。
たとえば、シャンプーのCMなどで、髪のキレイな女優さんを起用することで、仮にその女優さんが、実際に使っていなくても、そのシャンプーにいいイメージを与えるという手法なんかもありますよね。
一般的には「いいイメージ」を与える為の方法ではありますが、その女優が逮捕などされてしまうと、同時にシャンプーのイメージも引きずられて悪くなってしまうケースもあります。
芸能人が不祥事を起こすと、すぐに契約解除されるのはそのためです。
ハロー(Halo)とは「後光」という意味で後光効果を呼ばれたりすることもあります。
有名人を使うほどの資金がなくても、このハロー効果を活用したい場合には「権威のある人の意見を利用する」テクニックでカバーすることもできます。
化粧品などに「有名大学教授推薦」「〇〇研究所教授監修」というような、文言を付けて販売されている商品もたくさんありますよね。
今お話しした事例と同様に、すでに権威のある人の推薦文などを効果的に引用することで、あなたが仮に、まだ無名だとしても、発言に説得力を持たせることも可能になるわけですね。
例えば、「あの有名な〇〇さんに推薦していただきました!」というように有名な人の名前を借りることで、普通に紹介するよりも簡単に、あなたの商品の信用度を上げることも可能です。
ただし、このテクニックは使いすぎると、あなた自身のブランディングが出来なくなる危険もあるので、あくまでここぞというときのスパイスとして使うことをお勧めします。
テクニック9.ティーザー効果(広告)
9個目のテクニックは、ティーザー効果です。
ティーザー効果とは「情報を小出しにして読み手の好奇心を煽るテクニック」です。
人間心理として、すぐにすべての情報を渡されるよりも、少し焦らされてからのほうが満足度は高くなる傾向にあります。
このテクニックはゲームの発売時によく使われたりしますね。
僕も子供の頃好きだった「ドラゴンクエストシリーズ」は、
- 発売2年前くらいから情報の小出しが始まり
- ゲーム雑誌でちょっとずつ紹介していき
- 発売が近づくにつれて全貌が見えてきて
- もうちょっとで発売!というところで発売延期(笑)
- 焦らすだけ焦らされた人たちが発売初日にドラクエを求めて行列を作る
という流れが定番でした。
このように、あなたが何か商品を発売しようとした時に「発売しまーす」と一気に全て発表するのではなく、少しずつ小出しにしていくことで、お客さんの期待を高めていく際に使えるテクニックです。
テクニック10.カリギュラ効果
10個目のテクニックは、カリギュラ効果です。
カリギュラ効果とは、禁止されるほどやってみたくなる心理的効果の事をいいます。
カリギュラの語源は、かつて「カリギュラ」という映画が過激すぎて上映禁止になった事で、かえって話題になったというところからきています。
ギリシャ神話のパンドラの箱や、日本昔話の鶴の恩返しも同じですね。
ダメだといってるのに開けちゃうみたいな。
あえて禁止することでむしろ気になってしまうという状態を作り出すテクニックです。
このテクニックも、使いすぎると飽きられちゃうので、使う頻度やタイミングは考えてくださいね。
テクニック11.ドア・イン・ザ・フェイス
11個目のテクニックは、ドア・イン・ザ・フェイスです。
ドア・イン・ザ・フェイスとは、やり手のセールスマンがよく使うテクニックで「最初に高すぎるハードルをあえて提示することで、次に提示するハードルを低く見せるテクニック」です。
たとえば、恋人にディズニーランドに連れて行って欲しいと思ったときには、
彼女「今度の夏休みに、ハワイに連れて行って!」
彼氏「は!?海外なんて無理だよ」
彼女「じゃあ、ディズニーランドは?」
彼氏「うーん、ディズニーランドくらいならいいよ」
こんな感じで誘導できますし、職場の後輩にどうしても残業をお願いしたい場合は、
自分「〇〇さん、今日3時間ほど、残業お願いできないかな?」
後輩(まじか汗 勘弁してよ)「すいません、今日はどうしても都合が悪くて……」
自分「そっか~、30分でもいいんだけどお願いできないかな?」
後輩「ああ、30分くらいなら、何とかなりますよ」
という感じですね。
本来の目的はそれぞれ、
- ディズニーランドに行きたい
- 30分残業をしてほしい
なんですが、いきなり本来のお願いをするのではなく、あえて難易度の高いお願いをすることで、本来の頼み事が小さく感じられるので、承認してもらいやすくなるというわけです。
テクニック12.バーナム効果
12個目のテクニックはバーナム効果です。
バーナム効果とは、「誰にでも当てはまることを言われているのに、自分にだけ当てはまっていると勘違いをしてしまう現象」のことを指します。
バーナム効果がよく使われているのは「血液型を使った性格診断」などですね。
あなたもこんな性格診断を1度はやったことがあるはずです。
- A型は「綺麗好き」
- B型は「自己中」
- O型は「大雑把」
- AB型は「二重人格」
よく考えたら、大勢いる人間を4種類の性格に分けることは不可能ですよね。
でも、なぜか当たり前のように受け入れられているのも「バーナム効果」が影響しているわけです。
バーナム効果に関しては、下記の記事でも詳しく解説しています。
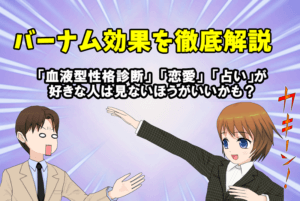
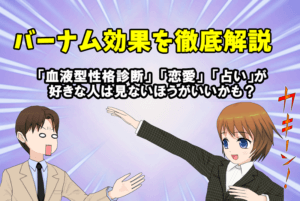
テクニック13.シャルパンティエ効果
13個目の心理テクニックは、シャルパンティエ効果です。
シャルパンティエ効果とは、同じ重さのモノは大きいもののほうが軽いと感じる効果のことをいいます。
たとえば、20キロのダンベルと15キロの段ボールでは、どちらのほうが軽く感じるでしょう?
おそらく段ボールのほうが軽いとイメージしたのではないでしょうか。
「軽さ」をウリにした商品などの広告では、シャルパンティエ効果を取り入れたものが多いです。
たとえば、商品を大きく見せたい場合「東京ドーム何個分」といった表現することがあります。
東京ドーム〇個と聞くと「何となく広い」と感じますよね。
逆に商品をの小ささをアピールする際によく使われるのが「タバコ」です。
タバコを横に置くことで、その商品の小ささがイメージしやすくなりますよね。
タバコ以外にも、硬貨なども大きさを表現する際によく使われています。
心理テクニック14.損失回避(プロスペクト理論)
14個目の心理テクニックは、プロスペクト理論です。
プロスペクト理論は、1979年にダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって発表された不確実性下における意思決定モデルのひとつ。
ひと言でいうと「人間は損をしたくないと思う感情」を持っているという解釈がプロスペクト理論です。
たとえば、カーネマン氏の実験の中であった実験では、
質問1:あなたの目の前に、以下の二つの選択肢が提示されたものとする。
- 選択肢A:100万円が無条件で手に入る。
- 選択肢B:コインを投げ、表が出たら200万円が手に入るが、裏が出たら何も手に入らない。
上記の質問では、どちらの選択肢も手に入る金額の期待値は100万円と同額ですよね。
それにも関わらず、一般的には堅実性の高い「選択肢A」を選ぶ人の方が圧倒的に多いとされています。
質問2:あなたは200万円の負債を抱えているものとする。そのとき、同様に以下の二つの選択肢が提示されたものとする。
- 選択肢A:無条件で負債が100万円減額され、負債総額が100万円となる。
- 選択肢B:コインを投げ、表が出たら支払いが全額免除されるが、裏が出たら負債総額は変わらない。
上記の質問に関しても、両者の期待値は-100万円と同額です。
普通に考えれば、質問1で「選択肢A」を選んだ人ならば、質問2でも堅実的な「選択肢A」を選ぶと思いますよね。
しかし、質問1で「選択肢A」を選んだほぼすべての者が、質問2ではギャンブル性の高い「選択肢B」を選ぶことが実証されています。
この一連の実験が意味することは、人間は目の前に利益があると「利益が手に入らないというリスクの回避」を優先し、損失を目の前にすると「損失そのものを回避しようとする傾向(損失回避性)」があるということ
心理テクニック15.カクテルパーティ効果
15個目の心理テクニックは、カクテルパーティー効果です。
カクテルパーティー効果とは、1953年に心理学者のコリン・チェリー (Cherry) によって提唱されたもので、多人数が雑談しているなかでも「自分が興味のある人の会話、自分の名前などは、自然と聞き取ることができる」現象のことです。
この現象を応用することで、消費者心理を刺激することができます。
たとえば、
- 「みなさん」よりも「あなた」
- 「あなた」よりも「○○さん」
上記のように、ブログやメルマガなどでは「1人の人に向けて書く」こと鉄則です。
これは読み手に対してあなたの書いた文章を「自分ごと」だと思ってもらうためのテクニックのひとつです
心理テクニック16.認知的不協和
16個目の心理テクニックは、認知的不協和です。
認知的不協和(にんちてきふきょうわ、英: cognitive dissonance)とは、アメリカの心理学者レオン・フェスティンガーによって提唱された理論で、自分の持っている価値観と矛盾する新しい認知(事柄)と出会った時に不快感を覚える心理現象のことです。
たとえば、この現象をセールスレターに盛り込む場合
- 常識を再確認する
- 常識を根底から覆す
- 新しい常識を伝える
このような流れで文章を書くことで、読み手の心を一気に引き込むことができます。
ダイエットをするためには、厳しい食事制限をして、毎日運動をしないといけないと思い込んでいませんか?
実は、美しくダイエットをするためには「厳しい食事制限」も「めんどくさい運動」もする必要がありません。
私自身、食事制限も激しい運動もせずに○○するだけで20キロの減量に成功しました。
実は、美しくダイエットをするためには「厳しい食事制限」も「めんどくさい運動」もする必要がありません。
私自身、食事制限も激しい運動もせずに○○するだけで20キロの減量に成功しました。
その方法とは、○○を使って、☓☓をするだけです。
このように伝えても、あなたは「そんなバカな」と思うかもしれません。
その方法とは、○○を使って、☓☓をするだけです。
このように伝えても、あなたは「そんなバカな」と思うかもしれません。
その疑問を解決するために、これから証拠をお見せします。
という具合に、読み手の常識を一旦壊してから、新しい常識を伝えることで興味を引くテクニックです。
まとめ.行動心理学を理解して読者の心を動かす文章を書こう!


今回の記事では、行動心理学を利用した「消費者心理をつかむテクニック」をお伝えしました。
今回お伝えしたことをもう一度まとめておきましょう。
- ゴルディロックス(松竹梅)効果
- AIDMAの法則
- 理想の未来をイメージさせる(ベネフィットを伝える)
- 両面提示の法則(メリットとデメリットを伝える)
- 希少性(限定性)の法則
- バンドワゴン効果(集団心理の利用)
- 返報性の法則
- ハロー効果
- ティーザー効果
- カリギュラ効果
- ドア・インザ・フェイス
- バーナム効果
- シャルパンティエ効果
今回の記事で大事なポイントは、上記のテクニックは「スパイス的に使う」という点です。
あまりにも頻繁に上記のようなテクニックを使いすぎると「胡散臭い文章」になってしまうので、「読者を正しい行動に導く」ための後押しとして「スパイス的に使うと効果的」なのです。
あなたが書く記事すべてに、下記のような記載がしてあったらどうでしょう?
- 「これはすごいです」
- 「心臓が弱い方は読まないでください」
タダの痛い人になっちゃいますよね。
オオカミ少年と同じで、使えば使うほど効果は減少しますので、ここぞというときに使うことをオススメします。
あなたの商品が本当にお客さんを救える良いものならば、「背中を押してあげる」ことも優しさです。
あなたが売らなければ、他社の粗悪品を買ってしまい不幸になるお客さんがいる可能性もあるわけですから。
うまくテクニックを使って、あなたのお客さんを救ってあげてくださいね。
では、最後までありがとうございました。


コメント